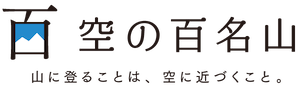山に登ることは空に近づくこと。
蔵王と言うとスキー場のイメージが強いですが、登山の対象としても魅力たっぷりの山です。
実は、蔵王山という名前の山がある訳ではなく、山形・宮城県境に連なる山並みの総称が蔵王連峰(蔵王山)です。最高峰の熊野岳(1,841m)や観光名所として有名な御釜がある北蔵王と、高層湿原があり、高山植物が豊富な南蔵王に分かれます。
写真1 霧氷に彩られる蔵王連峰

蔵王連峰は、南北に連なる山脈です。蔵王連峰の北西側には朝日連峰、南西側には飯豊連峰があり、西風が吹くとその間にある谷間に風が集中します。蔵王連峰に対して直角な西風を防ぐ障害物は無いため、摩擦の影響が小さくなり、風は強まる傾向にあります。
この強い西風が蔵王の名物とも言われる“モンスター”と呼ばれる樹氷をつくり上げます。
この強風が気象のリスクをもたらすことがあります。ロープウェイや車で簡単に山頂直下まで到達でき、手軽に登れる山のように思われますが、天気をしっかりと見極めることが大切です。
ある年の初夏におこなった観天望気を学ぶ講座のときには、刈田岳直下の駐車場で既に強風が吹き荒れていました。
このとき、上空にはレンズ雲が現れていました(写真2)。UFOのような不思議な形をした雲で、この雲は強風の兆候として知られています。
写真2 蔵王連峰上空に浮かぶレンズ雲

刈田岳を往復した後、熊野岳への縦走に向かいます。この間には、馬の背と呼ばれる、文字通り馬の背のように尾根が細くなっているところがあります。この付近は木どころか、草も生えない荒涼とした景観になっています。このように、植物がまったくない場所は強風帯であることを疑います(火山や土壌の影響のこともあります)。
山と山の間のへこんだところを鞍部(あんぶ)と言いますが、そこも風が強まる場所です。これらの場所を通るため、一旦、刈田岳の山頂に行き、そこでの風の強さを見てから進退判断をすることにしました。
このときは、天気が持ちそうなことと、気温が高かったこと、風も吹き飛ばされるほど吹いていないことや、これ以上は強まらない可能性が高いことから前進することにしましたが、メンバーの体調やルート状況(岩場や崖などがあるときは登山を諦めるなど)などを考えて慎重に判断しましょう。
蔵王連峰は、西に山形盆地、東に蔵王町など宮城県の平野部を経て太平洋があります。
山形盆地には秋から冬にかけての朝、雲海が広がることが多く、夏には雲が“やる気”を出して積乱雲が発生することが多くなります。また、太平洋からの風が吹くときには、濃い霧が発生することが多くなります。霧に覆われる前には、ジメッとした冷たい風が吹くことがあります。
山形県側と宮城県側で見られる雲が異なったり、両側で天気が大きく異なったり、気圧配置によってさまざまなパターンの天気が体験できることも魅力です。
あなたの登る日にはどんな雲が見られるでしょうか?
写真3 山形県側から押し寄せる雲

〇おすすめコース
空見を楽しんだり、蔵王名物の強風を体験するには刈田岳から熊野岳の往復や、地蔵岳への縦走がおすすめです。時間と体力に余裕があれば、北蔵王から南蔵王へ縦走すると、雲や風の変化を体感できます。初夏から夏にかけてはさまざまな花に出会えることでしょう。時間や体力に応じてコースを選べるのも蔵王の魅力です。